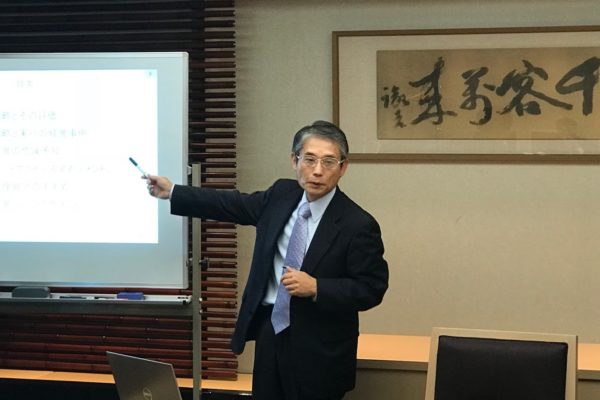- 2018年8月21日 UP
- マネジメント
『新志塾』第12期 2日目開催報告
2018年7月21日(土)、東京 渋谷にて『新志塾』第12期2日目の講義を行いました。
初めに、1日目の講義の復習も兼ねて、受講生2名に自社の経営理念について発表をしていただきました。お一人はこれまでパートナーと二人で事業を行っていたため経営理念を設けておらず、1日目の講義受講後にパートナーと真剣に話し合い経営理念を作られたということで、作りたての経営理念を共有してくださいました。新塾長からも作成した経営理念について直接アドバイスがあり、「更にブラッシュアップして完成版を作ります!」と気合が入っていました
新塾長は「理念は5年で振り返り、必要であれば修正する」ことを改めて伝え、経営理念はワーキングツールとして使い、生きた状態であることが重要であると説明しました。
受講生の発表後は、2日目講義のテーマである「リーダーシップと人材育成」について、新塾長の講義を行いました。
午前中は主にリーダーシップについて学びを深めました。新塾長が提唱する「ジンザイの4つの型」を学び、スキルもマインドも高い「人財」を組織の中に増やしたいのであれば、まずは自分自身が「人財」になる必要がある、と新塾長は強調しました。
また、各ジンザイの育て方や仕事の任せ方についても具体的に学び、特に「褒めることはしかることの4倍大事である」という内容に、受講生も大いに頷いていました。さらに、部下のやる気を高めるための動機づけとして、「聴く・決める・巻き込む・任せる・褒める・叱る・報いる・語り合う」という8つの行動が重要であり、受講生それぞれに何が足りていないのかを考えて、発表をしていただきました。

途中1時間のお昼休憩をはさみ、午後は具体的に「マインド(人間力)」をどのように高めたら良いのか、という点について講義を行いました。
新塾長は「人は結局、思ったとおりの人間になる」というゲーテの言葉を共有し、「スキルよりも情熱のほうが100倍重要である」と前置きをしてから、“情熱の5つの型”を紹介しました。また、情熱の火を燃やし続けるための3つの方法について「人生に目的を持つこと」「短期と長期の納得目標を持つこと」「点火人と付き合うこと」が大事であるとまとめました。
講義が一通り終了したあとは、これまでの講義の復習も兼ねて
「我々に求められるリーダーシップとは何か?」
「それをいかに開発し、発揮するか?」
というテーマで、グループごとにディスカッションの時間を設けました。インプットした内容をもとに、自分自身を顧みて、今後どのように改善していけばよいか、ということを声に出して話し合うことで、受講生も自身の課題について再認識し、考えがまとめられたようでした。

講義終了後には修了式を行い、受講生一人ひとりへ修了証書を授与し、2日間の感想を共有していただきました。
「これまでの人生、人に流されるままに歩んでいたことに気が付きました。今回学んだ長期と短期の納得目標を早速考えて、これからの人生をどのように生きていきたいのか、しっかりと考えていこうと決意しました」
「大変実用性が高い研修で、今の自分に足りていないことが明確になりました。特に、社員を褒めて育てるという点が全くできていなかったので、これから実行していこうと思います」
などのコミットメントをいただきました。

『新志塾』では、全期卒業生を対象とした勉強会を年に1回開催しておりますので、一段と成長した受講生の皆さんに再びお会い出来る日を今から楽しみにしています。日程は只今調整中のため、確定次第お知らせいたします。
次回『新志塾』東京第13期は、2018年11月10日(土)、12月8日(土)に開催いたします。
http://atarashimasami.com/shinshijuku/index.html
ご興味のある方は、是非ご参加ください。
投稿者プロフィール
この著者の最新記事
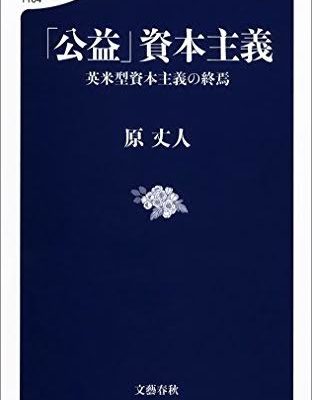
 マネジメント2020年1月15日【SDGs×100年経営】長寿企業が無意識に行ってきた持続可能な経営とは?
マネジメント2020年1月15日【SDGs×100年経営】長寿企業が無意識に行ってきた持続可能な経営とは?
 人材育成2019年12月13日ソーシャルプリンティングカンパニー®を目指す、大川印刷の挑戦!
人材育成2019年12月13日ソーシャルプリンティングカンパニー®を目指す、大川印刷の挑戦!